❤素人作家が自分で私家版の制作に挑んだ 自作の小説を単行本にしたい。 私がその「夢」を実現するには資金不足と言う絶対的な壁がありました。 現実を知ったのは所要15年という処女長編小説『小説太田道灌』を低予算で計画し、電子データありと言うことで、東京で働く友人に出版社の見積もりを取ってもらい180万という金額を知った時でした。 家計に無関係な私個人の貯金で済ます以上、即刻諦めたものです。 ただ数年を空けて一計を案じ、校正・校閲、ページ設定、ノンブルも付して一人で版下を制作、印刷と製本だけで見積もってもらえないかと遠方ながら県内西部にある印刷会社を訪れ交渉したところ快諾を得たのです。 300部で前記見積の実に7分の1という結果でした。 ちなみに装丁だけは知り合いのプロに頼んでいます。 その後かなりの年月を経て同様の手段で『夢の海』『キルリーの巣窟』を単行本化していますが、今回のお話はその詳報というよりは、私が採った方法の功罪というか成果の総括というか、そういう内容になります。 素人の本作りが夢ではないことをお知らせしたいからです。 私が発行した小説全ての費用についてお知りになりたい方はこちらからどうぞ(➡ sikabannohiyou ) もともと私の私家版発行は同人など知人への頒布と図書館などへの寄贈のためでしたが、地元の書店経営者の理解もあり店頭販売や電話受注などもしてくれたので一定数は販売としての成果もありました。 最も注目されたのは『小説太田道灌』で私の直接販売も含めると100冊に達しました。 まぁ、これは例外で読書離れの昨今、無名の素人の小説がそんなに売り捌けるわけがありません。 や はり所期の目的どおり頒布と寄贈中心になったものです。 ちなみに処女出版の寄贈図書館については詳しい記録が残っています(➡ otadokankizousaki ) やはり単行本となると読者の感想は多方面にわたり数も多くなって、反響があればあるほど発行の意義は立証されます。 自分でやることがかなり大変なことなので尚更なのです。
さて印刷屋から刷り終わった単行本が来て頒布、寄贈が進むのですが発行後に知ることができたことがいくつかありました。まず図書館に寄贈する場合1冊ではなく2冊になること、さらに国立国会図書館への寄贈は3冊となります。誰に寄贈しようがどこに寄贈しようがいつしか処分、破損、廃棄などで本がなくなる虞はあるのですが、この国立国会図書館は別ですので寄贈者の死後も遺り続けるというメリットがあります。寄贈すると受け取った旨の通知が来ました。(ほかの公立図書館では音無しも多々ありましたので扱いも色々なんでしょうが) また膨大な書籍を管理し閲覧請求にも便利なように記号番号が付けられます。『小説太田道灌』では書籍としてKH77-166でした。因みに同人誌『岩漿』も国立国会図書館に送っていますが、創刊号では書誌としてZ13-B770であり、最新号の31号では雑誌でZ71-V498とされて確かに保管されています。『孤往記』は唯一私家版ではなく出版社ありの仲間としてKH814-L452となっています。そうそう私家版も含め出版社により発行された本には「国際標準図書番号」(ISBN)というものがバーコードで本の裏表紙に13桁の数字で記されています。私の私家版3冊には当然ありませんが、『孤往記』には、ISBN 978-4-86543-053-0とあります。ところで本に定価の記載があるとなのですがISBNの下にもう一つバーコードが打たれています。「書籍JANコード」という日本独自の図書分類番号と価格コードなのです。私の本も定価は印刷されていませんのてこれは付いていません、価格が動くことを前提にしているためでしょう。もちろん私に価格設定権が無かったのであずかり知らないことですが。頒布と寄贈が目的ならどっちのコードも要らないでしょうというご意見も出そうですが、一つだけ「え?そうなの」と驚いたことがあります。実は自分の本ではなくずっと以前に買った本でしたが、引っ越しの整理のためとは言え廃棄は避けたいので古書店にもっていった中の二冊だけ、値段如何ではなく引き取らないというのがありまして、係員は2冊とも裏表紙にして見せて「コードがないから」といったのです。本来の書籍流通の対象にならない、ということなのでしょう。勉強になりました。 著者が自作の単行本化に成功し勝手な満足感と大いなる興奮に包まれたとしても世間の人が皆同じように感じ祝福してくれるわけではありませんし、その本を期待を籠めて各所に無償で頒布し寄贈したとしても、別に相手方が皆待っていたわけでもありませんし喜んでくれる訳でもありません。このことは冷静に覚悟しておいた方が良いと敢えて申し上げておきます。もちろん受贈先からきちんと受贈通知が来ることや、それだけでなく読んでくれて感想をしたためて返信してくれる人もあり、その喜びは何にも勝るのですが、経験からすると発送した先からの各種反応は全体の3割程度でした。そのうち感想までいただけたのはさらに3割程度になります。ただ、最後まで深く読み込み評論家並みの真摯な文で批評が来ることはその数云々ではなく自費出版の成果と言えると思います。因みにその例はこのHPのベージ4に載っています。あと単行本ではなく同人誌『岩漿』を図書館に寄贈したときのことでしたが、館員の声ではっきりと「こういう本は廃棄処分にしています」と言われたこともありますので、もしかしたら単行本でも起こりうるのではないかと思っています。書籍番号が無い私家版ならなおさらの虞になるかもしれません、そうです古書店での経験のように。ちなみに伊豆半島の図書館では大丈夫だと信じています、当地のように正規の小説棚ではなくとも「郷土の本」という棚で公開されると思いますので。廃棄という処分を受けたトラウマで、『キルリーの巣窟』発行時では図書館寄贈の範囲を静岡県東部あたりまでに縮めています。観光ホテルの倒産を扱っているということで、本当は一番読んでもらいたい地域なのに反発を避ける目的が勝ってしまいました。出版動機を誤解される恐れが多分にある作品でもあったので。今でも我が家の本棚に数多く残っている私家版の本はこのキルリーの本です。さらに一般の書店でも私家版はあまり歓迎されません。ただ、この場合でも郷土の書店では少しく様子が良い方に変わります。書店は言わば流通書籍を扱うプロ、売れ筋の本が「良い本」なので仕方ありません。それで思い出したのが、著名出版社の電子書籍の公募に応じた時のプロ(編集者)の言葉でした。その出版社から発行する電子書籍として採用する、つまり有名な出版社発行というブランド取得ということだったのですが、①タイトルはこちらで変える②登場人物の謎の動きが大分先の方で読者に分かるような進め方なのでこちらで変える、と決めていました。変えていいですか?というニュアンスではなく編集者の当然の権利という風でした。経費額が私の経済的な許容範囲を超えていましたので残念ながら辞退しましたが、私の作品を完読したうえでの真摯な評論文にプロとしての「視点」を感じその自信溢れる姿勢にある種の感動を覚えたものです。当時採用された小説というのはこのページの中にリンクがある『無彩色の森』でした。以上私家版発行にまつわるあれこれを経験をふまえ記しました。読んでいただき感謝いたします。(2024/3/28)
 耐えて萎れた梔子(くちなし)が男の墓で蘇る💛『未開封』
耐えて萎れた梔子(くちなし)が男の墓で蘇る💛『未開封』 ♥17-1未完の小説『未開封』p1-27➡ mikaifuu の本編 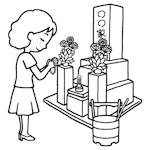
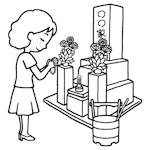
❤17-2完『未開封』(epilogue)p28-35を補正/完➡ mikaifuu4
 とりあえずどう?
とりあえずどう? ❤総括 自作を整理する結果になったこの「蛙声の游び場」ですが、とくに気になった小説について雑談風に記してみたくなりました。 しばらくお付き合いください。 ◆過去3作の私家版と1冊のamazon販売本を出していますが、最も売れた本は調査から脱稿まで15年を要した『小説太田道灌』で300冊刷って100冊超となり国公立図書館への寄贈91冊と並べて私的には効果がはっきりと出ました。 もともとは道灌(どうかん)に限らず発行は販売目的ではなく図書館、友人、同人等への寄贈・頒布でした。 半年を過ぎたころでしたか、歴史的にどうかとか我が地域にも道灌は関係したのに触れていないなどの指摘を受け困惑しました、この作品本当は『蛟竜(こうりゅう)の角』と命名したのですが、資料がほとんどない武将なので創作で補うしか方法がなく敢えてタイトルに『小説…』と冠していたのですが、それでも出た「抗議」でして、以後私は歴史上の人物を題材にしなくなりました。 或る歴史小説家はたとえ史料をはじめとする資料を集め揃えたとしても小説にするにはその大半を捨ててかからなければならないと語っています。 ◆『夢の海』は執筆当時参加していた東伊豆町の同人誌『碧(あお)』の原稿として前半部分を用意していたもので、書籍化をするについては、その後参加していた小田原文芸の同人の方に電子データ化などで大変お世話になり、辛辣な指導ながら勉強になった点においては最高の思い出になりました。 ◆発行した本の中で小説として最も読みやすい記述になったと評されたのは『キルリーの巣窟(そうくつ)』でした。 ただこの本は図書館への寄贈が一番少ない本になっています。 刷ったのも200部でした。 観光ホテルの労使の方に読んでほしいとの執筆動機でしたが、目的が果たせたかは不明です。 『夢の海』と『キルリーの巣窟』はいまだに伊東市内の書店に並んでいます。 これは書店の厚意でとのこと、感謝をしています。 ◆『孤往記(こおうき)』は初めてプロの手を借りて出版し今もamazonで購入可能になっていますが、価格が本の体裁も含めてみて高めに設定されているとの指摘があり、販売部数が最も少ない作品になっています。 執筆動機が貧しさのために高校、大学とも昼間部に入れず昭和の激動の中で世間に完全に取り残された主人公の迷いや孤独を同窓生に知ってもらいたかったというにあり、少し姿勢自体に問題ありだったかなという気がしています。 今は亡き恩師に「これは君の伝記?」と訊かれましたが、伝記の形を採った小説ですと答えています。 登場人物、特に5人の女性はまるごと虚構で私の青春時代に彼女らのような人いませんでした。 真実の伝記にすれば必ず第3者を傷つける結果につながります、男女を問わずイメージモデルがいいところでしょう。 しかし余命が短くなった昨今、本当の意味の伝記を書きたくなってはいます。 自分自身の総括のために。
◆総合文芸誌『岩漿』に掲載に掲載した小説では、実験的に「こんなのはどう?」とばかりに、『冷川峠』のように落語風に語ったり、『戯れる木霊(こだま)』で狂った女や『薪樵る(たきぎこる)』で霊に憑かれた男を扱ってみたりいろいろ試作しましたが大多数の短編は「愛とは何、家族って何」という共通の底流に添い比較的真摯に(笑)プロットを重ねました。 個人的に好みな自作は私が編集長をしているときではなく、それを辞してからに多く存在します。 すでに亡くなっている男が謎解きの中心に居るという相続話の『ヘクソカズラの遺産』は起承転結の工夫に多くの力を注ぎましたし、別れた男の葬儀に出かけ深夜に独り棺に寄り添って眠る女の複雑な心を描いた『逮夜(たいや)の女』は実際の通夜の雰囲気を大事にしたということで「お気に入り」になっています。 意外に思う人は多いのですが、警察の取調に限って言えばかなり警察ものを扱っているんです。 『心の音』はそれが物語の中心になっていますし、『ヘクソカズラの遺産』もそうでした。 取調より捜査・推理がメインになる作品については自分でも不思議なくらい燃えました(笑)『狗(いぬ)にあらず』の前・後編や岩漿には長すぎるので投稿しなかった『連環(れんかん)』などがそれで、読むと不思議に体まで熱くなるんです(笑)生と死についてもかなりの作品の中で間接的には記しましたが直接踏み込んだのは短編では『やさしい姫鼠( ひめねずみ)』と『くぐもり声』で、長編では最新作の『無彩色の森』になります。 長編はもちろん『岩漿』外で5冊目の本にする予定でした。 この作品では愛って何、家族って何、生と死の繋ぎ目は何、のすべてに斬り込んでみました。 後期高齢にならなければこれは書けなかったと思います。 自分の最期が身近になって初めて見つめられる部分がある。 そう思うからです。 私は作者の家族や親族を題材にして書いた小説が好みではなく、自作でも例外的に『雪積む樒(しきみ)』で私と母のことを、また『朴(ほお)の葉の落ちるころ』で私と長兄のことを書いたにすぎません。 しかも後者は本人の依頼を受けての創作でした。 まあ、私の家系の場合、誰を採っても小説になるほどの波瀾万丈な人生なのですが、だから尚更題材にしたくなかったのです、見聞してきた事実だけでお腹いっぱいで。 或る同人から私はエンタメ系の小説書きと言われていますし「そういえばそうだな」と納得もしています。 じつはこの企画で意図的にとりあげなかった作品があります。 理由を挙げて並べてみます。 小説の中で解説している学説や法規が古くなってしまったという中編の『ツール』、指摘を受けたのは知り合いの法曹からでした。 じつはそういうことを未然に避ける工夫というのがあります。 創作段階で作中の事件があった時期、年代が分かるような台詞や地の文を入れておけばいいのです。 そうしなかった私のイージーミスでした。 次いで、最新設備を施したホテルを舞台にして設備主任だった男がタイムスケジュールで動く機器を利用して起こす密室の犯罪を扱った『心裡の解鎖』(しんりのかいさ)がそれで、犯罪の解き方が煩瑣に過ぎたからでした。 なんにせよテクニカルタームは厄介ですから読み物としては如何なものかという反省からです。 すべからく創作上の苦い経験は先々の肥やしなのですが、発見は公開後に第三読者として読み直さないとなかなか気づけないんです。 なにしろ脱稿した段階でもう浮き上がっていますから(^^♪ 以上で勝手な総括は終わりですが、最後に申し上げたいのは創る、書くって苦しい場面もありますが楽しいですよ、意外と、創作過程でいつもと違った自分に出遭ったり、人物関係図を作っていると人や物事を多角的に見詰める良い癖がつきますから。 生来短気な人も、つまり私もですが、知らぬ間にイライラしたりすぐ腹を立てたりなどが減っていきます。 これは趣味文芸のご利益だと実感しています、ハイ。 もう一つ、創作物を公開したとたんにそれらは「一人歩き」を始め読者それぞれの受け取り方をするということで、もしかしたらそれは作者自身が気づかなかった「自分再発見」に繋がるかもしれません、ぜひお試しください。 ではまた。 (2024/2/29)
 ちょっと喫茶
ちょっと喫茶 このページを創り月毎に少し毛色の違う自作を掲げてから早いもので16か月が過ぎました。ほかの頁に掲げたものと併せると馬場駿の小説がほとんど全てあるということになります( 私の全作品➡babasakuhinichiran )。43年ほど前に山梨の里山で偶然に知り合った国立大学の先生と『岩漿』や私の創作本など文芸を通じてお付き合いが続いていたのですが、彼には、私の文芸活動は趣味ではなく私の生涯の「かたち」であり「生きた証」であろうという意味のことを告げられたことがあります(この先生との関係性はGoogleでこのHPを検束すると判ります)。そのときからすでに10数年、何だか私自身もそうかもしれないと思うようになりました。このページはその想いの表白なのかもしれないと。特に脳梗塞罹患後退院してからはほかのことが何もできない事情から文字通り文芸三昧の日々をおくっていたと言え、元国語教師の旧友から羨ましいとさえ評されました。その間の総仕上げとも言えるこの無名の同人誌作家のHPを訪れてくださった方々には感謝の言葉しかありません、大いなる励みになっていたのですから。キツイと感じた回もあったのに継続できたのもそのお陰です。 ところで電子データのない旧作の全頁打ち込みは、ブラインドタッチならいざ知らす雨垂れ打ちの上に眼疾もあったので難儀でした。もつとも苦難ばかりかと言えば違います。旧作の欠点や不足を現段階のレベルで改編したり再校閲できたからです。まるで他人が創作したように感じるほどの第三読者の目で作品を熟読玩味できたのは貴重な経験でもありました。その過程で、かねて指摘されてきた漢字の数をできるだけ少なくすることや普段使わない漢字の訓読みについては( )内にルビ代わりの仮名表記をすることなど昨今の読者傾向に対応したりもしています。紙媒体の文芸が激減しSNSで用いられる文体も大きく変わりました。私だけでなく交流している詩や短歌の会の同人の方々も近い将来紙媒体の文化・文芸が衰退していくのではないかと憂えています。一方で危機感を抱いた人たちが全国規模で頑張ろうとしている姿も力強く存在します。一例として九州に本部を置く「文芸同人誌案内」をご覧ください。まだまだ頑張れるぞと力をもらえます。➡ http://hiwaki01.sakura.ne.jp
 コーヒーはブラックだったのでケーキをいかが?
コーヒーはブラックだったのでケーキをいかが? 冒頭で掲げた先生に同人誌『岩漿(がんしょう)』を毎号寄贈していたのですが彼はこんなことを何度か書き送ってくれています。「これを読んでいると何か落ち着くんです」と。学生たちの文章に日々触れていると何かが変わってしまったような気がするということらしいのですが、実は私も当時は編集もしていましたので同感でした。同人から「文章に昭和を感じる」と言われている私ですから若い書き手からすれば逆も亦真なりでしょうか。擬古文(ぎこぶん)、言文一致、旧仮名遣い、漢字制限、片仮名外国語の氾濫、差別用語の使用禁止など、言葉も文章も時代を追って変遷を促すあれこれが出てきましたから世代間で感覚が異なるのは自然だとして受け取るべきかもしれません。「言葉は生きている」として納得してもなお昨今の文化や世相は文芸の世界を転生させる勢いを感じます。 ちなみにその流れを危惧させる現象を順不同で単語のみで羅列してみます。すでに知られているものばかりなので注釈は無用だと思いますので。電子メール、SNS(フェイスブック、インスタグラム、ツイッターなど)、SMS、ブログ、匿名サイト、電子書籍、Kindle、スマホ、配信、炎上、ライトノベル、電子版、コミケ、軽薄短小、英語日本語共に略語の氾濫、言葉狩り、学生・女子高生などの符丁、原作コミックの脚本、プライバシー、流行語、掌編、ためぐち、ハラスメント、漢字離れ、ツンドク、英語重視、国語審議会、キラキラネーム、活字離れ、LGBTQ,読解力、OECD調査、本屋大賞、自動変換、AI… これらが何で、どう文芸の転生、あるいは破壊につながるのかはご推察ください。アバウトに論じて参りましたが、変化が不可避ならそれはそれとして一つの時期乃至時代に活きていた文芸の型はそのまま残すべく真摯に取り組めばいいのではないかと、そんな風に思います。 ****自前のホームページであることをいいことに全編にわたり少し生意気なことを書きすぎたかもしれません。ただ、「蛙声(あせい)」には「つまらぬ者のいう言葉」という意味もあると或る書物で知って「ピッタリじゃん」と自虐を含め人生最初の筆名にしました。解りにくいと評された私を唯一信じてくれた経営者の名前「馬場駿」を筆名に使わせていただいた今も愛着を持っている所以です。いずれまたページを増やし違った挑戦をしたいと思っています。ご支援、ありがとうございました。2024/1/28
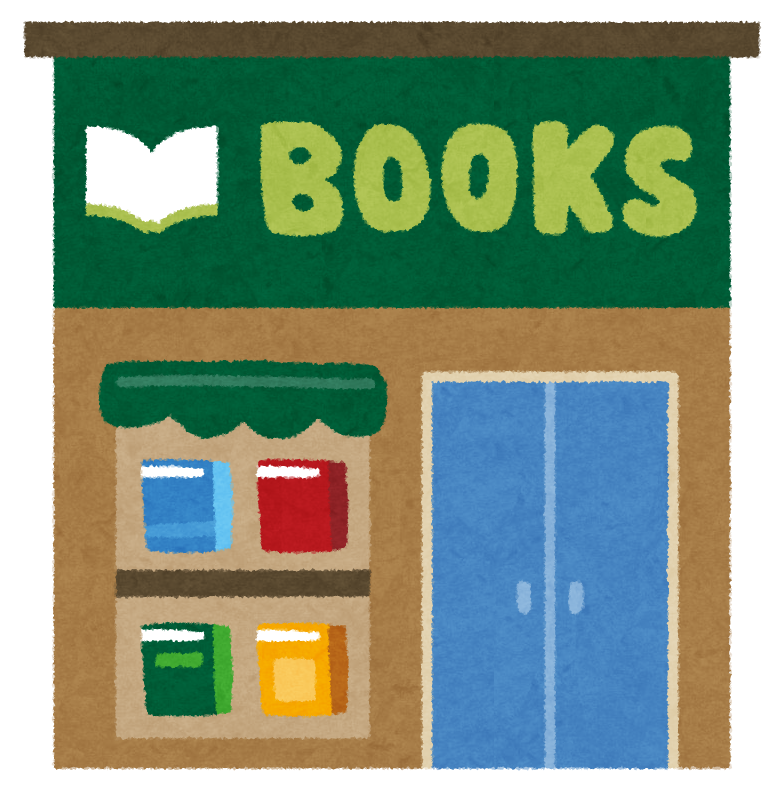 💛(^^♪ここの本棚常時開架中
💛(^^♪ここの本棚常時開架中(16)💛『無彩色の森』(むさいしょくのもり) 5冊目の作品にと1年半に亘って執筆した人生最後の長編小説。追い詰められながらも矜持をもって死を見詰める人たちとその「家族」の葛藤を描く。 ➡ musaisyoku
15)『耄老の海』(ぼうろうのうみ)1997年 医院3代目の息子を支えていた佳江の許に民生委員から命の恩人で初恋の男哲郎の便りを受け取り現地に飛ぶが彼は乞食同然の病人だった ➡ 2bourounoumi
(14)『罪の連関』2020年 ー罪を犯したのは連続殺人犯二人だけなのか― 県警の捜査一課に警部補と部下二人だけという小チームが生まれ謎だらけの事件を推理を重ねて解明してゆく ➡ tuminorenkan
(13)『ヘクソカズラの遺産』2018年 サスペンス仕立てで描く。愛と信頼で囲まれながらそれを最後まで解からず哀しく独り佇むことになる女文子。死んだ夫が主人公という珍しい創り➡hekusokazuranoisan
 ヘクソカズラの花
ヘクソカズラの花(12)『小説・現姥捨て』2016年/増補2023年 近未来の妄想小説。雑誌記者が超高齢者社会の世相を福祉課勤務の先輩に訊き、追い詰められた老夫婦に密着して書いた記事は上司の命に背いていた➡imaubasute2
(11)『色あせたデコイ』1997年/改編2023年 出所した女が温泉場の女将に拾われ更生に勤めるが周囲の偏見は止まず加えて女将の異常な嫉妬もあり、それが因で宿主が女将を銃殺する事件が起こる➡decoy2
(10)『超克』(ちょうこく)2000年 脳梗塞患者がみた診療病棟とリハビリ病棟。そこには自身と戦う患者と医療スタッフの心の交流があった。登場人物の無様からの超克は新たな視点での再出発から➡tyoukoku
(9)『薪樵る』(たきぎこる)2000~23年 男は病死した不倫相手の影を追い不仲の妻を殺して女との出会いの場鎌倉へ。全ては妄想なのか霊なのか女との逢瀬。男は終に惚けて迫り来る電車の前に➡takigikolu2
(8)『身一つ庵』(みひとつあん)1998年 家庭と職場のことで心病んだ男は、泊った民宿で献身的に働く障碍者女将と過去のある宿主の夫婦に当たり散らし、泥酔した翌朝に心癒されて我が身を省みる➡mihitotuan
(7)『孤往記』amazonで販売 (こおうき)1999年 伝記の形をとった小説。孤独で貧しい青年が激動の昭和の大都会を喘ぎながら活きてゆく姿は著者の過去と多分に繋がっている。第1章のみの掲載➡koouki
(6)『朴の葉の落ちるころ』(ほおのはのおちるころ)2013年 いまは亡き兄の依頼でしたためたモデル小説で彼は自分のブログで公開した。緑内障で全盲を覚悟した彼が手術を漸く決める姿➡hoonohanootirukoro
(5)『狗にあらず』(いぬにあらず)2003年 事件を任せられる警官は彼だけだ。元妻が狙撃された男はその謎を解くため単身行動を起こすが、事件はただの殺人ではなく国政すら絡む巨大組織の陰謀➡inuniarazup
(4)『空に映る海の色』(そらにうつるうみのいろ)2009年 東京の会社社長の息子が滞在先の多賀で高熱の少年を助けた縁で母親と恋仲になるが、彼女の一族の奇怪な男女関係が突然彼の身に及ぶ➡soraniuturuumi
(3)『戯れる木霊』(たわむれるこだま)2007年 暴漢に襲われていたのを救おうとドデカイ犯人に挑んで死んだ彼氏。自分の操は彼の命ほどの価値はない。その想いが彼女を狂わせる➡tawamurerukodama
(2)『傾いた鼎』(かたむいたかなえ)2015年 同じ時期を青年3人が性を含む複雑に絡んだ感情の渦をそれぞれの視点で捉える試み。誰も傷つけない青春、そんなものが果たしてあるのか➡ katamuitakanae
(1)『入相の鐘』(いりあいのかね)1995年 落ち目の画家と元妻の人気作家の仲にいつの間にか挟まった天真爛漫で美形の若いモデル。それにモデルの彼氏が絡んだ激しくも哀しい愛の三つ巴を描く➡iriainokane



